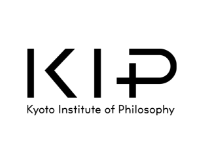【京都会議ハイライト1】「幸せ」「善さ」自明ではない 「価値の時代」の多層性とは ――出口教授 基調講演(前編)

産業界と学術界の垣根を越え、18か国から2日間で延べ600人が参加した第1回京都会議―「価値多層社会」の実現に向けて―。政府・自治体、外交界、宗教界、民間団体などの関係者も加わり、AI隆盛の時代背景を踏まえて「価値」に関する哲学的思索を深めました。この先駆的試みをハイライトで振り返ります。
Details
ニュース・記事内容
18か国から600人 「危機感」胸に臨む議論
二重三重の円を描くように馬蹄形に机が並んだ国立京都国際会館の大ホール。9月23日午前9時、第1回京都会議は俯瞰的な現状分析の言葉から始まりました。
「産業界のリーダーたちは、変化と予測不可能な世界において社員に意識を変えるよう呼びかけてきました。しかし、意識を変えることは容易ではありません。価値観という核となる層を変えなければ、意識は変わらないからです。一方、学術界、特に人文学や哲学の分野の方々は長い間、産業界や現実社会に十分関与してきませんでした」
京都哲学研究所の共同代表理事を務める澤田純NTT会長の開会あいさつです。澤田会長は産業界と学術界それぞれが直面する高い壁を指摘したうえで、次のように京都会議への意気込みを語りました。
「だからこそ、この会議では分野を越えて語り合うきっかけを生み出したいと考えています。新しい世界の価値観を発見したいと思います」
会場に鳴り響く拍手がやんだ後、京都府の西脇隆俊知事ら開催地・京都を代表する方々やジュリア・ロングボトム駐日英国大使ら来賓の代表者が順番にスピーチを行いました。語り口こそ静かなものの、それぞれの言葉には地球規模で人類が直面している諸課題への強い危機感がにじみました。
西脇知事「環境問題、少子化問題、国際情勢の不安定化など大きな社会課題が存在し、それらが複雑に交差する一方で、技術革新のスピードは非常に早く、AIをはじめとする新技術が社会に与える影響は日々増しています」
ロングボトム大使「とりわけ、AIや量子技術といった新しいテクノロジーから生じる問題、さらには安全保障上の新たな脅威や気候変動による影響に私たちは直面しています。これらの課題は、私たちの倫理的・理性的な枠組みの限界を試し、人間とは何か、ビジネスとは何か、政府や国家とは何かといった根源的な問いを私たちに突きつけています」
ハイレベルな領域横断の議論が、行動へと昇華していくことを期待する声もありました。ペトラ・ジグムント駐日独大使は「私たち自身で進むべき方向を考え、望ましい未来を形作るために、意味ある行動を起こす方法を探らなければなりません」と国際的連帯を呼び掛け、京都会議を共催した京都大学の湊長博総長は「混迷と分断の困難な時代を乗り越えていくための明確な方向性と、希望のあるビジョンを国際社会に向けて発信していただきたい」と述べました。
京都哲学研究所は、今回の会議を「根本的な価値の問題を探求する場」と位置付けました。相互に連関する複合的な課題は、もはや従来の技術的・政策的アプローチだけでは解決できません。複雑化・深刻化した課題の根源に立ち向かうには、私たちが進むべき方向性そのものを問い直す必要があります。根源的な問いの核心にあるのは、私たちが何を重要で、望ましく、正しいと見なすかという「価値」です。議論のベースとなるこうした考え方を参加者の皆さんに理解していただくため、澤田会長と並ぶもう1人の共同代表理事、京都大学の出口康夫教授が20分余りの基調講演を行いました。大型スクリーンの前に立った出口教授が、ゆっくりと近代のパラドクスから紐解き始めます。
対立・矛盾も包み込む 大切なのは認め合うこと
「20世紀、人々は科学技術が進歩し、経済が成長すれば幸せになる、そう信じて歩みを続けてきました。しかし、人々は必ずしも幸せにならない、社会は良くならない、戦争は後を絶たない。一方で、そもそも幸せとは何か、社会の良さとは何か、価値とは何か。こういった問題が自明でないということに我々は気づきつつあるのではないでしょうか。価値、理念といったものが行方不明になっている。チルチルとミチルの『青い鳥』のように不在になることで、ますます存在感を増している。今、我々はそういう時代、価値の時代に生きているのではないかと、私はそう考えています」
そもそも、価値とは何でしょうか。出口教授の見解はこうです。
「私は京都哲学の伝統を継ぐ形で、価値を身体行為と関連付けて考えたいと思います。価値とは、何かをすることによって求めようとしているもの。言い換えると、価値は身体行為に対して一定の方向性を与えるベクトルの役割を果たしている。みんなが同じ価値を掲げることで、その方向性が揃って共同行為が初めて可能になる。価値とはそういうものです」
出口教授は当研究所のリレーインタビュー(本サイトに掲載中)で、「価値があるから行為はまとめることができる。価値は行為に明確な方向性を与えるベクトルそのもので、人類の共同行為を可能にしている接着剤」であるとも語っています。だとすると、人類が向かうべき共通のベクトルは存在するのか、そんな疑問を持つ方も少なくないでしょう。出口教授は講演で言いました。
「唯一の正解はありません。個々人が方向性を持つ。個々の社会が独自の方向性を持つ。それが重要です」
そのうえで、私たちが留意すべき点として「異なった価値のベクトルが、場合によっては対立したり矛盾したりするケースも抱え込んでいる」ことを挙げ、そのような実態を認識することが「多様性、多元性を超えた価値の多層性」だと強調しました。価値は一つではなく、多層である。多層性を理解し、認め合うことが大切ではないか――。出口教授は講演で参加者に問いかけ、こう続けました。
「京都哲学研究所の1つのミッションは、価値の多層性を肯定して、多様で多層な価値を提案し、それを実装した価値多層社会を実現することにあります」
出口教授基調講演・後編へ続く――
Others