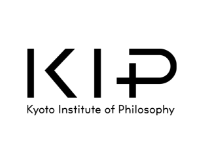【京都会議ハイライト2】青臭く問い立て潜行・浮上 今こそ「WEターン」思考を ――出口教授 基調講演(後編)
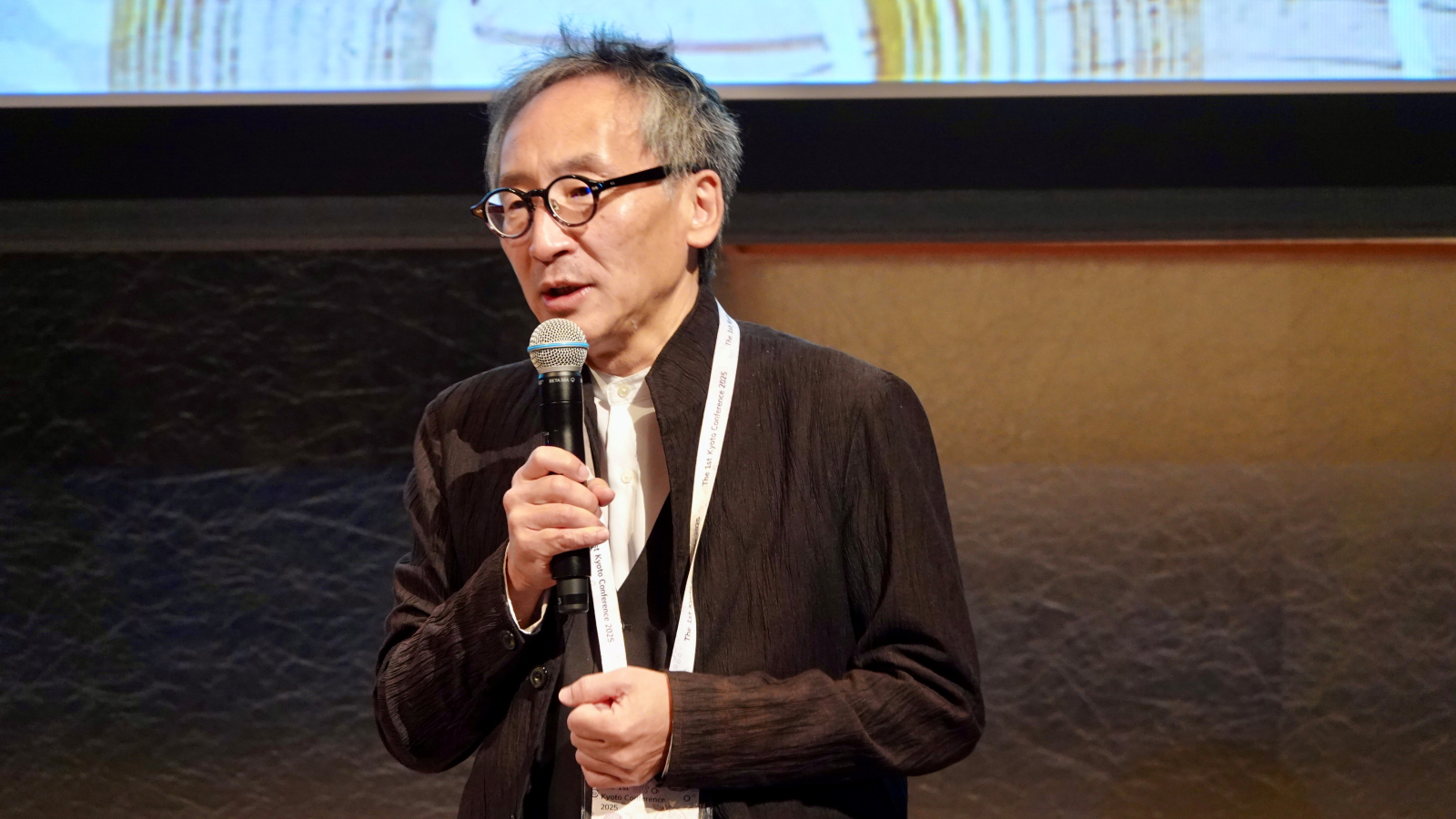
出口教授は京都会議の議論の土台を形づくる基調講演で、「潜行」と「浮上」という二つのキーワードを強調しました。その理由とは――。講演は後半に入ります。
Details
ニュース・記事内容
哲学・人文学の役目とは――新たな「価値」で社会とつながり
「価値とは何か、人間とは何か、社会とは何か、世界とはどうあるべきなのか、いわば青臭い問題を改めて問い、根本に戻って潜行する。考えたものを社会の実践に持って来るために、今度は浮上する。ぐるぐる回って循環する、円環する。そういった活動をするしかないのです」
出口教授は基調講演の中盤で語気を強め、そう語りました。潜行と浮上は、京都哲学研究所が京都会議来場者に配布した資料「コンセプトペーパー」に盛り込んだ大切な概念です。当研究所が名付けた「ABCモデル」を前提にしています。ABCモデルは、現代の課題を駆動するメカニズムを「分断」と「変容」の二つの力学で捉え直し、それを乗り越えるための思考法です。AはActionの頭文字で「目に見える実践」を示し、CはCoreの頭文字で「根底にある価値観」を意味します。BはBridgeの頭文字で、AとCを繋ぐ制度や文化様式などのことです。
出口教授は基調講演で、問題の根本原因へ思考を深めるAからCへの潜行と、新たな価値から未来を構想するCからAへの浮上を繰り返す往還運動こそ、産業界と学術界が手に手を携えて実践すべき活動ではないかと提起しました。そして往還運動を率先するために哲学者が果たすべき役割について、こう自覚していると明かします。
「哲学・人文学は、科学の知見を踏まえたうえで具体的な価値を社会に提案するのが大きなミッションです。もう一度、価値を提案する。そういった営みを通じて社会にエンゲージする。今そういうことが求められているのではないかと考えています」
出口教授が提案する「価値」の一つがWEターンです。WEターンは、「わたし=I」は1人だと何もできないという根源的なできなさを認識し、自分は常に「われわれ=WE」の一員であるとの視点にターンして(立ち返って)思考することを言います。なぜ、今この時代にWEターンの思考法が必要なのでしょうか。出口教授はその理由について、西洋の思想家3人を比較しながら説明します。
「古代ギリシャのアリストテレスは『知的にできるもの』が『できないもの』を一方的に統治・支配する、逆に言うと『知的にできないもの』が『できるもの』に奉仕するといった関係こそ理にかなっており、両者の得にもなるのだと主張しました。そして、階層の上にいるものたちを主人、階層の下にいる人たちを奴隷と呼びました」
「冗談じゃない、と言ったのが18世紀の啓蒙主義の哲学者カントです。カントに言わせれば、人間は全て生まれながらに知的に平等・同等だ。カントは奴隷制に反対し、民主主義、民主制が一番いいと主張しました。でも、カントは人間と人間以外の動物の間にはやっぱり知的にできる、できないといった差が厳然として存在し、人間が動物を支配する、動物が人間に一方的に奉仕する関係は当然だと主張しました」
「カントの考えに、冗談でしょう、と言ったのがニーチェです。彼はアリストテレスが言ったように、できる、できないの差が存在すると言い直したわけですが、ここからがニーチェの面白いところ。ニーチェは一方で、主人の座を巡る人間のあくせくしたゼロサムゲームを軽蔑して、現実・現状をどれだけ悲惨なところがあったとしても丸ごと肯定する、現実肯定力を身につけた超人になるべきだという新たな価値を主張しました」
優劣に着目すれば危うさ 「できなさ」に見る尊厳
ここで出口教授は聴衆の世界観をAI隆盛の現代へと引き戻します。声のボルテージが一段あがりました。
「ニーチェ主義は、今日でも色々な方々が唱えています。例えば、テック右派とされるカーティス・ヤーヴィンさん、哲学者ニック・ランドさん。彼らは暗黒啓蒙を主張し、人間には知的に、よりできるエリートと、そうではない一般大衆がある。エリートが直接的な参政権を持つ寡頭政治こそがふさわしいと主張しています。さらに、この会議の大きなテーマであるAI。AIやロボットは、まだ自分たちをデザインすることができません。この一線を守ることで、人間が主人、AIやロボットが奴隷だと。これはまさにアリストテレスの言葉ですけれども、そういった関係こそがありうるべき関係だという『主人-奴隷モデル』が現在でも主張されています。私の『WEターン』は、できないことに人間の尊厳、かけがえのなさがあるとの主張ですから、アリストテレスの考えに逆張りすることになります」
出口教授は講演でWEターン思考の背景についても説明し、「東アジアの聖なる愚者の伝統がある」と述べました。「役立たずの象徴である木偶の坊になりたい。そう書いた20世紀の日本の詩人・宮沢賢治にも伺える考えです」と説き、同じWEでも「良いWE」と「悪いWE」があると指摘します。
「悪いわれわれの一つの典型例は、全体主義的なわれわれです。外に対して排外的、中に対して抑圧的。抑圧的なわれわれの、これまた1つの典型例が独裁者、特権的な社会の集団です。他のメンバーが全て周辺に追いやられ、中心と周辺の間に一方的な支配―被支配、統治―被統治、奉仕―被奉仕の関係が設定されている。中心占有的WEが悪いわれわれの典型例です」
ならば、良いWEとは――。出口教授は静かに答えます。
「中心を意識的に占めさせない、中空的なWEです。WEターンでは、より平等な、身体行為という冒険に共に参加をしている共冒険者モデル(フェローシップモデル)を提案することになります」
壇上を左右に動きながら語り掛けていた出口教授の動きが、ぴたりと止まりました。
「とはいえ、WEターンも多層的な価値の一つでしかありません。この会場には世界から様々な価値観を体現されている方々がお集まりになっています。1日半の会議を続けて価値多層社会へと1歩でも踏み出す。ぐるぐる回りの循環、円環運動。そのきっかけになればと願って、基調講演を終わります」
Others