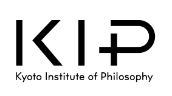【リレーインタビュー2】 澤田純NTT会長(下) 京都会議「相違と合致を楽しむ場に」 連携の輪 広げモメンタム加速
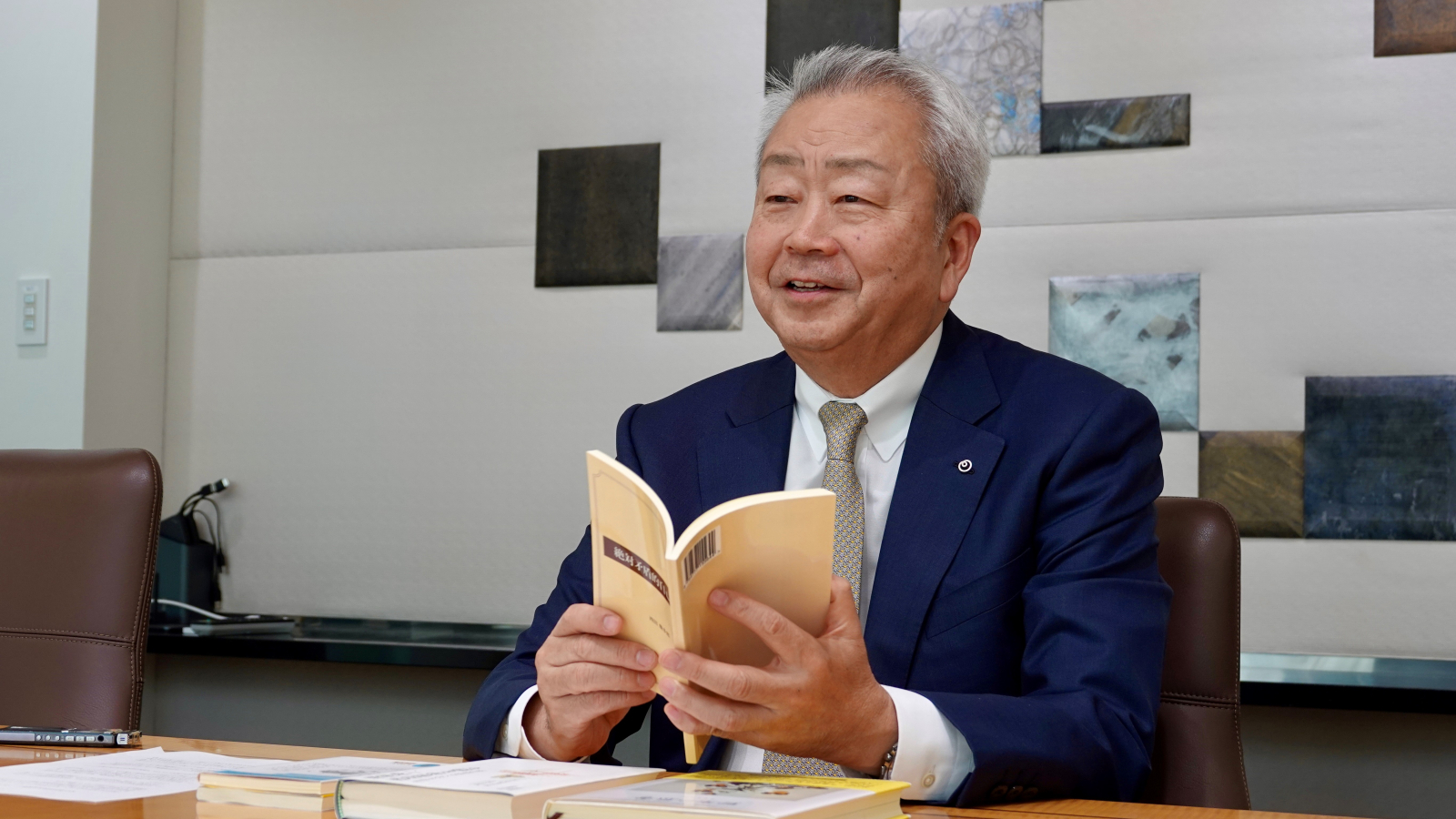
澤田純共同代表理事インタビュー連載の「下」です。
Details
ニュース・記事内容
――澤田会長は京大工学部卒で理系専攻でありながら、歴史や哲学に造詣が深いですね。
哲学には学生時代から色々トライはしていました。けれど、ダメでしたね。家にあった西田幾多郎の『善の研究』も、挑戦しては跳ね返されました。読んでも意味不明だったりしてね(笑)。ただ、学生時代に乱読したことは、それによるセレンディピティ(思いもよらなかった偶然がもたらす幸運)もあったので、良かったのかもしれないです。だけど、本が増えると妻から「家が傾く」とか言われてね(笑)。最近はもっぱら電子書籍です。
歴史書だと、井沢元彦にはかなり影響を受けました。梅原猛の『隠された十字架―法隆寺論―』、梅棹忠夫の『文明の生態史観』、それを引き継いだ川勝平太の『文明の海洋史観』も勉強になりました。あと、衝撃を受けたのはユクスキュルの『生物から見た世界』です。ユクスキュルが提唱した「環世界」という概念に私は注目しています。
――生物によって見えている世界が違うという概念ですね。当研究所のシニア・グローバル・アドバイザーを務める独ボン大学のマルクス・ガブリエル教授も著書『なぜ世界は存在しないのか』で、人によってそれぞれの世界が存在するから、単一の「世界」というものは存在しないという話をしています。
ええ、人間にも「環世界」は当てはまりますよね。非言語コミュニケーションが不可能なSNSが、それを助長している部分があります。
――ガブリエル教授が唱える「倫理資本主義」については、どのように受け止めていますか。
私は肯定的です。「全部他人のため」は嘘だし、「全部自分のため」は強欲すぎます。私がよく言うのは「半ば自分のため、半ば他人(ひと)のため」。ガブリエル教授の主張に重なると思っています。
ただ、倫理資本主義をどう実装するかというところは結構難しいですよね。たとえば、会社法などにそういう視点を入れていくとなったら、企業のステークホルダー同士で利益相反になった時、倫理やモラルが何物にも優先すべきだとするのかどうか。そういった議論はまだまだ必要かもしれません。
――9月23、24日の2日間にわたって開催する第1回京都会議には、哲学者だけでなく産業界を含め幅広い方々に来ていただく予定です。どのような会議にしたいですか。
先日、会議に招待したある経営者から、こう聞かれました。「いったい何をしたらいいでしょう。話せと言われても、哲学のことなんか全くわからないし」と。私はその方に「色々な方が色々なことを言うので、それを勉強してください。京都会議は、そういう会ですから」と申し上げました。
強調しておきたいのは、京都会議が「解」を用意することはないという点です。「京都哲学研究所はこう考えます」みたいなものは提示したいなと思いますが、それに対して参加者の皆さんから様々な意見が出るでしょう。多様な意見を聞きながら一人一人に考えていただきたいのです。
京都会議には「価値多層社会」を巡って考え方の近い哲学者、企業人もたくさん集まります。しかし、アカデミアと産業界では使う言葉が違うことでしょう。どういう切り口で整理して考えるのか、どこにドライブをかけるのか。人によって異なりますから、違いを楽しんでください。
「解」は多分、京都会議に参加したいと思ってくださっている人の中に、もうありますよ。自分の意見、自分の価値観が会議に参加している最中にちょっと揺さぶられたら、それでOK。意を強くされてもOKだし、自分の価値観が違ってストレスと怒りが起こってもOKです。
――第1回京都会議が終わった後も研究所の活動は続きます。どこを目指していくのでしょう。
出口さんがまた良いことを言われていて、「1人では何もできない」と。その通りだと思います。当研究所だけでは何もできませんから、世界中から議論に参加してもらって、中空構造のフェローシップ的な運動体を作る、そのモメンタムを加速させていくというのが次の目標です。海外の組織・団体で私たちと連携協力を模索する動きも幾つかあります。そうした人たちと手を携えながら、どこまで運動体を形成していけるかですね。
京都会議では企業、アカデミア、そして個々人のレベルで、それぞれが何をすべきかといった議論が湧き上がってくるはずです。私は将来的に「京都宣言」を出せればいいなと考えているのですが、皆さんから出た意見の共通点がどこで、対立点はどこかというのを構造的に書き落としていけば、それが「京都宣言」の素案になっていくでしょう。
Others