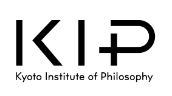【リレーインタビュー2】 澤田純NTT会長(上) 科学とAIが死生観変える——哲学創造へ突き動かした危機感

当研究所の主要メンバーに、活動を始めるに至った経緯や今後の取り組みへの思いをリレーインタビュー方式で聞きます。2人目は共同代表理事を務める澤田純NTT会長です。
Details
ニュース・記事内容
――京都哲学研究所の創設を思い立った経緯を教えてください。
2010年代にiPS細胞(人工多能性幹細胞)を巡る議論が活発になったことがありました。iPS細胞は病気やけがで失われた組織を新しい細胞で補うもので、再生医療への応用に対する期待が大いに膨らみました。それと同時に私が予見したのは「人間の寿命は変わっていくのだろうな」ということでした。そして2018年に邦訳が出版された『ホモ・デウス――テクノロジーとサピエンスの未来』で歴史家のユヴァル・ノア・ハラリは、こう近未来を予測しました。
「21世紀には、人間は不死を目指して真剣に努力する見込みが高い」
「21世紀には、データ至上主義が世界観を人間中心からデータ中心に変えることで、人間を主役から外すかもしれない」
私は「人間を含む生物は、死なないと地球の生態系に貢献できない」と考えるので、生死のサイクルは大事にしなければならないと思っています。しかし、ハラリが言うように生命科学と人工知能AIの発展によって不老不死の人間が誕生するなら、「人は死なない」という前提で物事を考えなくてはならなくなります。そしてAIにも「死」は訪れません。私はiPhoneが登場した時に「色々なものが根こそぎ変わるかもしれない」と直感したのですが、ハラリの本を読んで、それを絶する強い危機感にさいなまれました。
NTTが2019年に構想を発表した次世代情報通信基盤「IOWN(アイオン)」は、AIの進化を加速させるインフラです。私は通信事業者の一人として「IOWNの開発に合わせて社会需要側の社会学が必要になる。それは、すなわち哲学だ」と考えました。
ただ、西洋哲学を基礎にしても無理だろうなと。思案の末、京都学派の西田幾多郎の哲学に行き着きました。日本哲学会の中では独特のものですし、世界でも認められていますからね。そこで当時、京都大学の総長だった山極壽一先生に「西田の流れをくむ方は誰かいませんか」と尋ねたのです。そして紹介を受けたのが出口康夫教授でした。
出口さんと初めて会った時、私はIOWNの話をしました。すると出口さんは「それは新しい社会インフラです。新しい哲学がいりますね」と言うのです。いい言葉だなと思いました。
――その後、澤田会長から出口教授に研究所の設立を持ちかけ、「新しい技術には、新しい哲学を」が当研究所の共通認識の一つになりました。なぜ「新しい哲学がいる」という結論に達したのか、澤田会長の思考過程をもう少し詳しく教えてください。
実は2023年9月に出口さんとエストニアを訪問した時も、意見交換した方から「『新しい技術には、新しい哲学がいる』というのは、非常にクリアなように見えて、なぜかを言えていない」と同様に指摘されたんですよ(笑)
説明しましょう。世界には「気候変動」「格差」「分断」など多くの社会課題がありますよね。たとえば、それらの克服をゴールに位置付けて考えてみてください。大きな壁が立ちはだかっている社会課題を解決するには、何が必要だと思いますか。人々の行動や社会規範(ルール)を変えることだと思います。しかし、行動やルールはなかなか変わらない。それは意識改革が進んでいないからです。意識を改革できない原因はどこにあるでしょう。私に言わせれば、価値観が変わらないことが最大の要因です。
実は、この種の議論を出口さんら研究所のメンバーとしたことがあります。出口さんはその時、「価値観の基にあるのは人間観なんです」とおっしゃった。人間観って、まさに哲学じゃないですか。つまり、社会課題の解決方法について深く掘り下げていくと、哲学に行き着くのです。これを出口さんの言葉で動的なイメージで表すと、社会課題のところからダイナミックに哲学まで潜水して、ゴールまで浮上していく――という感じになります。潜水と浮上の往還移動には大きなエネルギーと熱量がいりますよね。ですから、まずモメンタムを作り出すことが必要だと思っているのです。
先ほどの「新しい技術には、新しい哲学を」の話に立ち返ると、NTTがIOWNの開発に取り組んだのは、中央集権的なシステム基盤ではもう対応できなくなってきたからで、課題を起点に下へ下へ潜っていくと、やはり「新しい哲学」の必要性が見えてきたというわけです。
――産学連携の取り組みは国内外に数多ありますが、京都哲学研究所の独自性はどこにあるのでしょう。
なかなか珍しい連携だと思っています。産業界から見れば、哲学って儲からないんですよ。哲学には生産性がないので、企業とは対極にあると思われていますから。「あんなもんは役に立たんやろ」と言われたりもします(笑)
一方で、京都哲学研究所の仲間になってくださった博報堂、日立製作所、読売新聞などの企業トップの方々は、企業活動や資本主義を広い意味で捉えていますよね。強欲に、とにかくカネを稼げばいいんだというところを超えて「それじゃダメだよね」と。
同じ文脈で導き出されたのがマルチステークホルダー論であり、倫理資本主義です。ただ、制度や経済を論じる前に、「どう人間観を考えていくか」という哲学がないと、先ほど言ったように社会は変わらないんですよ。こうした意識の一致が当研究所設立の根底にあり、それが独自性を生み出していると思います。
Others