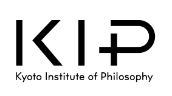【リレーインタビュー4】 戸田裕一・博報堂相談役 新時代メディアの意味や価値とは 創造・尊厳めぐる議論、京都会議に期待

当研究所の主要メンバーに、活動を始めるに至った経緯や今後の取り組みへの思いをリレーインタビュー方式で聞きます。4人目は理事を務める戸田裕一・博報堂相談役です。
Details
ニュース・記事内容
――なぜ京都哲学研究所に参画したのですか。
研究所の共同代表理事を務める出口康夫京都大学教授と澤田純NTT会長のお2人は「新しい技術には、新しい哲学がいる」とおっしゃっています。実は私も以前から「新しいコミュニケーション、新しいメディアには、新しい哲学がいる」と考えていたんです。
博報堂の生業はコミュニケーションです。コミュニケーションは「メッセージとメディア」という二つの要素で構成されます。メッセージは、意味を伝えて関係を作るもの。そしてメディアは、関係を作って意味を伝えるものだと言えるでしょう。つまりコインの表裏の関係なのです。
この二つの要素について論じたカナダの研究者がいましてね。マーシャル・マクルーハンです。私が一橋大の学生だった頃、マクルーハンのメディア論が注目を集めました。彼は「メディアそのものがメッセージである」と主張した。メディアが意味を持っているということを初めて言った人だと思います。彼の主張が正しいとしたら、メディアが持つ意味や価値を明確化しなければならない――。私はずっと問題意識を持ち続けてきました。
メディアの歴史を紐解けば、言葉が文字になり、文字が印刷になり、印刷が電子メディアになりました。そして今、AIやメタバース、デジタルツインといった新しいメディアが登場し、時代が変わろうとしています。だからこそ今、新しいメディアが持つ意味や価値について皆さんと議論させてもらいたい。そう思って京都哲学研究所に参画させてもらいました。
――戸田相談役がコピーライターとして言葉と向き合い哲学的思考を巡らせてきたことも、研究所参画につながったのではないでしょうか。
そうですね。もう一つ、ご縁があるなと思うのは、弊社の企業フィロソフィーと、京都学派の西田幾多郎に師事した哲学者・三木清との結びつきです。三木は『生活文化と生活技術』という著作で「生活者」「文化」「技術」が一つながりになるような論を展開しました。弊社のフィロソフィー「生活者発想」の根本にも、人々を単なる消費者として捉えるのではなく、 自らの生活を主体的に組み立てている生活者として捉えましょうという発想があるんです。
――人間の創造性を尊ぶ広告会社から見ると、AIの急速な進化は脅威ですか。
それについては社内で2、3年前に議論したことがあります。あるクリエイターはこう言いました。
「人間の頭脳が行う全ての思考を100に置き換えると、AIは1から99までを代行するようになるでしょう。 しかし、『0から1』の間と『99から100』の間はAIにはできません。『0から1』は、過去を否定して新しいものを作るクリエイティビティの領域だからです。そして『99から100』は、自らの責任で未来を選択し自己決定するという人間の尊厳の領域だからです」
私は、なるほどなと感心したものです。「99から100」に関する考察は、人間が責任主体になることの重要性が改めて浮上するという見方です。自らの行動を決める自由を説いたカントの発想にもつながります。
――人間の尊厳にまで考えを巡らす哲学的な議論ですね。
「0から1」については最近、さらに一歩進んだ議論が社内で行われ、こういう意見が出てきました。
「生成AIは、別解を探す相棒である」
AIは正解を得る道具ではない。別解を探す相棒としてAIとは協創関係になっていくんじゃないかという面白い意見で、私は共感できるなと思っています。クリエイティビティの領域では、正解が一つだとは限りません。別解が複数あっていいんですよ。
実は、生成AIに同じ質問をし、どんな答えが返ってくるか試してみたこともあるんです。私は、こういう尋ね方をしました。
「クリエイティビティを『意義ある新しい形態を生み出す能力』だと定義した場合、AIは脅威になるだろうか」
生成AIはこう回答しました。
「AIが生成した形態に人間が意味を与えるならば、それは協創です。でも、AIが形態と意味を同時に生成し、人間が受け身になるのなら、それは脅威です」
なかなかの回答で驚きました(笑)。9月の第1回京都会議では、そうした考え方について参加者の皆さんからぜひ意見を聞いてみたいですね。
――SNSを含むインターネット社会の問題点については、どう考えますか。
これは私の造語になりますが、インターネットは「渦型モデル」だと言えます。そして新聞、雑誌、テレビ、ラジオは「滝型モデル」です。滝型は高い所から低い所に水が流れていきます。情報水位を高く保たなければならないので、新聞やテレビなどは、すごくプロフェッショナルになってくると思うんです。
一方の渦型は水位がフラットで、回転エネルギーで渦を作るようなコミュニケーションの形になっています。サッカーのパス回しみたいなものだと考えてください。よく言う「炎上」はパス回しが過熱した状態。「バズる」はパス回しが盛んになって渦が拡大した状態です。
問題はフィルターバブルやエコーチェンバーのように渦が閉じてしまうことです。閉じた渦と閉じた渦が非和解的で、分断を起こしている。では、開かれた渦にしていくにはどうしたらいいか。閉じた渦と閉じた渦を結びつけるために何をすべきか。私たちが議論すべき課題です。
ネットは「標的型モデル」でもあります。プラットフォーマーがデータを収集し、顧客の内面を探ってパーソナライズする。これによってフィルターバブルやエコーチェンバーが起きているので、標的型の負の側面についても踏み込んだ議論が必要ですね。
――京都会議では価値多層社会についても意見をかわす予定です。
価値多層社会は、相異なる価値観を尊重する非常に包摂的な考え方です。1人の人間の内面だけでなく、共同体や社会、あるいは国家や国際関係も複数の価値が層を成して積み重なっていますよね、という見方が根本にあります。マーケティングの世界でも、「十人一色から十人十色になり、いずれは一人十色になっていく」と言われてきたのですが、実際そういう世の中になってきたわけです。
ただ、世界は今、地球温暖化や新型コロナのように1国1地域だけでは解決できない、複雑な課題に直面しています。価値の多層性を認めつつ、世界規模の課題に足並みをそろえて取り組むには、「価値多層社会を成り立たせる秩序は何か」という問いを立て、答えを導き出さなければなりません。
デカルト以来の個人中心の西洋的価値観で、この秩序を見つけ出すのは難しいでしょう。その点、出口教授が提唱する「WE-turn」は東洋的というか、「I」が中心ではなく「WE」が主体だという価値軸の転換から始まっていますよね。もっとも、西洋でもアダム・スミスは『道徳感情論』の中で共感の重要性を説きました。これは「WE-turn」に通じる考えだと思いますので、西洋的思考か東洋的思考かという二者択一で秩序を考えない方がいいかもしれません。
――若い頃から哲学的思索が好きだったのですか。
いえいえ。学生時代は社会学専攻でしたし、京都哲学研究所に参画した当初は議論についてくのがやっとでしたよ(笑)。だんだん出口教授の言っていること、たとえば「Self-as-WE」とか「WE-turn」っていう言葉が好きになっていったっていうか、最近は自分のもののように感じられるようになってきたかなと。
――京都会議の来場者にも同じ感覚を持っていただけるでしょうか。
会場で聞いた言葉を自分なりに置き換えてみたり、独自の解釈を加えて違う表現にしてみたり。言葉は咀嚼していくうちに理解につながっていくもので、それが面白さだと思うんです。参加者の皆さんには、そんな面白さを体感していただければ嬉しいなと思います。
Others