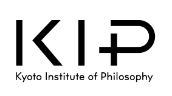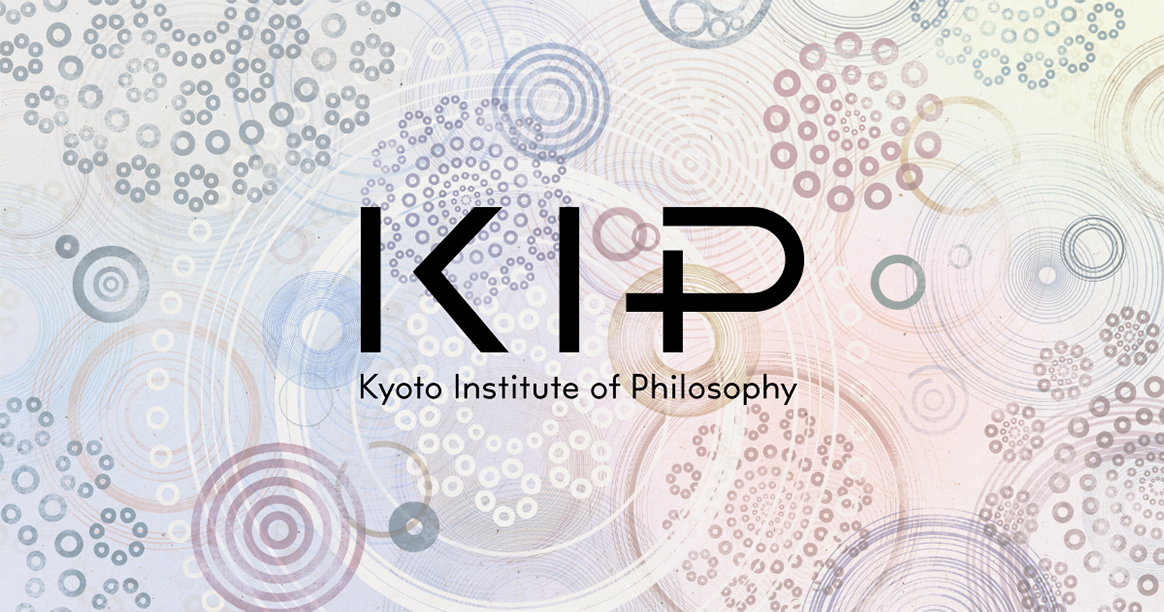【リレーインタビュー5】 山口寿一・読売新聞グループ本社社長 「ジャーナリズムは人間的活動」 AI時代にヒューマニズムとらえ直す
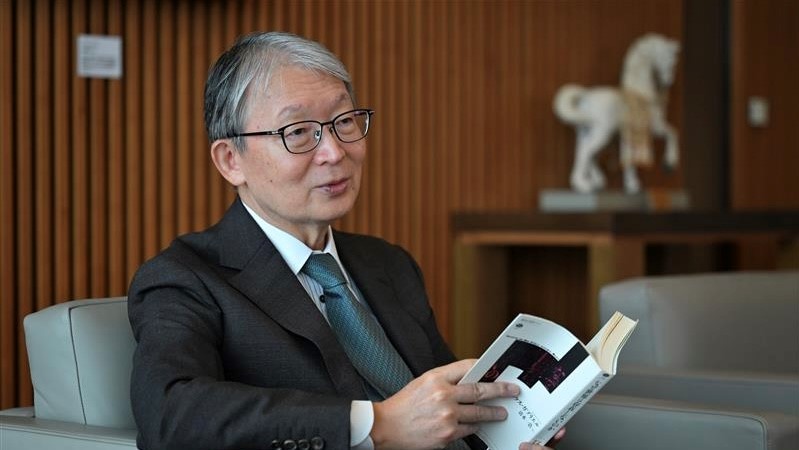
当研究所の主要メンバーに、活動を始めるに至った経緯や今後の取り組みへの思いをリレーインタビュー方式で聞きます。最終回の5人目は理事を務める山口寿一・読売新聞グループ本社社長です。
Details
ニュース・記事内容
――京都哲学研究所に参画した経緯を教えてください。
2023年のことですが、Chat GPTが世界に急速に広がったことに危機感を覚えまして、私は生成AIの利点と危うさを整理して、規律と活用の両立を求める提言を行いたいと考えました。そこで澤田純会長にご相談しました。澤田さんは、私などよりずっと早くから問題意識をお持ちで、AIを巡る問題について深く考察されていました。
澤田さんのおかげで読売とNTTは、生成AIのあり方に関する共同提言を2024年4月に公表しました。この過程で京都哲学研究所のお話をお聞きしたんですね。「新しい技術には新しい哲学がいる。日本の哲学、東洋の思想を基礎に置く」との考えにとても共感したので、お仲間に加えていただきました。
――第1回京都会議の主要テーマの一つは「AIが問い直す『人間』」です。読売新聞社は報道機関としてヒューマニズムを大切にしていらっしゃいますが、AIの出現がヒューマニズム、ひいてはジャーナリズムのあり方にどのような影響を与えると見ていますか。
読売新聞社は、読売信条という報道機関としての誓いを掲げています。自由主義と人間主義と国際主義の3つの理念が読売信条の柱です。
読売の考える自由主義は、自律の自由です。読売信条では「読売新聞は責任ある自由を追求する」と宣明しています。自律の自由と言っても無私・利他の精神を強く意識しているので、「ゼロサムゲーム的自律」には当たりません。出口康夫先生の考える自由に近いと感じています。
人間主義は、西洋にのみ通用する人間観ではなくて、真に普遍的な人間主義、文明の衝突を超えたヒューマニズムをめざしています。国際主義は、宗教や民族に優劣をつけず、争いを避けて世界の平和と経済的安定を築いていこうという協調主義です。
1946年に作られた旧信条には「左右両翼の独裁思想に対して敢然として戦う」との一文がありました。新旧いずれの読売信条も、全体主義の抑圧や排外を廃して、ゼロサムゲームを脱した協調的世界をめざしている点で、繰り返しますが出口先生の考え方に近いと思います。
AIはヒューマニズム、ジャーナリズムに確実に影響を与えます。従来、人間固有のものだった活動がAIに代替されるということが起きつつあります。科学技術を用いて生物学的な限界を超えた人間を生み出そうというトランス・ヒューマニズムが現実味を帯びて、人間と機械の区別がつきにくくなっています。
人間の尊厳を巡って、EUはAI法を制定して、たとえば従業員の採用や評価に関するAIの使用はハイリスクだとして、ハイリスクAIの要件を厳格に定めて、人間による監視を要求しています。一方、アメリカは州レベルのAI規制の動きが急増して、2024年には45州で693件の法案が審議されて113件が成立しました。これに対してトランプ大統領はAI規制排除の大統領令を発しました。連邦と州で異なる方向の政策が進んでいる状態です。AIを巡る考えがばらつく状況では、マンとマシンの関係はどうあるべきかという問いを立てて、ヒューマニズムをとらえ直すことが必要でしょう。
ジャーナリズムの役割は、人々の耳目の延長、精神の延長になることです。そのために記者は自分の耳目で見聞きしたこと、自分の精神で感じたことをそのまま押し出すのではなくて、読者になり代わって取材して、読者の耳目によって見聞きしたこと、読者の精神によって感じたこととして記事を書き、伝えることが求められます。
ジャーナリズムが伝えるのはニュースで、ニュースとは人々が知っておくべきこと、人々が関心を持つであろうことの総称です。しかし、人は未知のことには関心を持ちようがありませんから、記者は読者の関心の向くところを推量して、情報を取捨選択して記事を配列していくことになります。こうしたジャーナリズムの性質を考えると、ジャーナリズムとは、人間=記者が、人間=読者の公共的関心や公共的利益を手探りしながら行うもので、極めて人間的な活動と言えます。
現代ではSNSがジャーナリズムとは別の基準を用いて情報伝達をします。その基準はアテンション・エコノミーと呼ばれて、人々の平均的関心へ収斂する方向ではなくて、特定の関心を刺激して特定の意見を増幅させる方向に作用します。このため現代のジャーナリズムは、先入観を持ち特定の意見を持っているオーディエンスへ向けてニュースを発信する難しさを抱えています。そこにAIが絡んできます。AIはSNSの機械処理を加速させて、情報の爆発的拡散に拍車をかけます。偽情報の問題がますます深刻になるおそれがあります。
――その偽・誤情報は、AIの高度化で一層見分けがつきにくくなりました。それらがSNSを通じて瞬時に世界に拡散し、分断を引き起こしています。新聞社として、この問題にどう向き合いますか。
偽情報に関する研究で知られているのがマサチューセッツ工科大学の研究です。2006年から12年かけて、300万人のツイッターユーザー、450万回のツイート、12万6000件のニュースを対象に拡散状況を調査しました。ニュースを正しい情報と偽情報に分けて、どちらがより拡散したか調べたところ、偽情報の方がリツイートされる確率が70%高くて、偽情報は正しい情報の6倍の速度で拡散していることが分かりました。要するに、人は偽情報や陰謀論が好きなんですね。SNSのアルゴリズムが、その傾向を強めます。その結果、偽情報が真実であるかのように多くの人に信じ込まれるといった現象が実際に起きます。
この問題に対処しようと、読売新聞社と慶応大学と電通が中心になって、インターネット上の情報の発信者を明示して、その発信者に第三者機関の認証があればそれも表示する「オリジネーター・プロファイル」と呼ぶ技術の開発を進めています。
ただ、こうした取り組み以上に新聞社が力を入れるべきは、やはり正確なニュースでしょう。社会学者の清水幾太郎は、ジャーナリズムと流言飛語を対置して、「ジャーナリズムが機能しているのはノーマルな状態、ジャーナリズムが不足して流言飛語が飛び交うのはアブノーマルな状態」と述べました。新聞社は正確な報道という原点を肝に銘じなければなりません。
――山口社長は哲学書をよく読まれますか。好きな哲学者はいますか。
哲学書は比較的読む方だと思います。主にジャーナリズムについて考える観点から、カント、ミル、デューイ、ポパー、和辻哲郎、河合栄治郎などを読んできました。マルクス・ガブリエル教授も好きで、よく読んでいます。
――第1回京都会議では、「価値多層社会」についても意見を交わします。どのような議論を期待しますか。
近代以降、西欧文明の世界化が進んで、グローバル化という頂点まで来て、行き詰まりを迎えているのが現状だと思います。価値観に優劣をつけて従属させる従来のやり方では解決がつかず、争いが不可避になりかねません。価値多層主義という、共生の新しい考え方を打ち出すのは大きな意義があります。
東京大学名誉教授でメディア論の石田英敬さんは「ポリフォニックな共生」という考えを示しています。ホモフォニーでなく、ましてモノフォニーではない、ポリフォニーのような議論が交わされることを期待しています。
Others