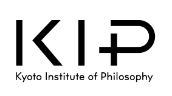【リレーインタビュー3】 東原敏昭・日立製作所会長 哲学無くして経営成らず——「未来の社会」見据え研究所参画

当研究所の主要メンバーに、活動を始めるに至った経緯や今後の取り組みへの思いをリレーインタビュー方式で聞きます。3人目は理事を務める東原敏昭・日立製作所会長です。
Details
ニュース・記事内容
――京都哲学研究所に参画した経緯を教えてください。
NTTの澤田純会長から誘われたのがきっかけです。日立製作所は今、鉄道や送配電システムなどの社会インフラシステムをデジタル技術で高度化し、暮らしの質を向上させる社会イノベーション事業に取り組んでいます。目指す方向は「誰ひとり取り残さない、人間中心の社会」の実現です。その未来社会の形はどうなっていくのか、自分の中で考えていた時、澤田さんから研究所設立のお話を伺いました。色々な価値観が混ざり合い、お互いに認め合って「幸せとは何か」を考える。そんな「価値多層社会」を実現しようとしているというので、我々の目指す未来社会と共通するところがあるなと。これはいい機会だということで研究所に参画しました。
――以前から問題意識をお持ちだったのですね。
産業界はこれまで、ものづくりが主体でした。今は、CO₂をどう削減するか、どうやってプラスチックゴミを最少化するか、フードロスはどうすれば減らせるのかーーといった社会課題の解決に産業界も取り組まなければいけない時代です。
ここで大切なことは、3つあると考えています。まずは主体性です。たとえば、飲み終わった後のペットボトルをどうするか、自分ごととして考えること。2番目に大事なのは共感力です。世界中で取り組みを展開するには、相手の文化とか宗教とかバックグラウンドを理解することが必要です。そして3つ目は、人を巻き込んでいく包摂性です。社会課題の解決といった大きな取り組みは1人ではできないですし、1社でもできません。NPOなどの団体や市民1人ひとりを巻き込んでいくことが大切です。
――日立製作所は創業の地・茨城県日立市で、デジタル技術を活用した新たな街づくりに市と連携しながら挑戦していますね。東原会長が言う「市民を巻き込んだ活動」の先駆けと言えそうです。
「日立市を良くしたい」という思いをつなぐ市民参加型の取り組みです。「次世代未来都市共創プロジェクト」と銘打って2023年12月、市と包括連携協定を締結しました。「こういう社会にしよう」と決め、それに向かって着々と近づいていく。日立市民の皆さんには「自分は社会にこんな貢献をした」ということを実感してもらえるような形を作りたいと思っています。何らかの指標を作って、その達成度を測ることができたら、ますます頑張ろうという気になりますよね。
京都哲学研究所が目指す方向も同じだととらえています。色々な価値観を持った人が「考え方は違っても、これは地球課題だから、みんなで努力しよう」という思いを共有し、具体的な取り組みに結びつけていく。研究所でまとめるコンセプトも、いずれ日立市の共創プロジェクトに入っていけばいいなと思っています。
――東原会長が強調する共感力は、著書『日立の壁』で説いている「利他の心」に通じます。
日立の創業者・小平浪平の言葉に「正直者であれ」があります。これ、非常に重くてね。創業から百十数年後の我々経営陣も、意思決定する時に「自分の利害を超えて、会社や社会のためになる。そういう気持ちでいるのか?」「正直者なのか、お前は?」と常に問いかけられているような気がしています。
でも、全く無の境地で相手に尽くせるかというと、それが「究極の利他」ではあるのですが、実際はなかなか難しいですよね(笑)。だから私は社員に「相手もウィン、自分もウィンになるようなことを考えてくれませんか」と言うんです。相手のウィンを考えるということは、すなわち「相手の立場に立って考える」ということ。ある意味では共感力なんですよ。
――社会貢献を強く意識する経営者が最近増えていると聞きます。
増えているとともに、両極端に分かれていっているという気がしています。ショートタームで見る企業家や投資家はまだ結構います。一方で、ロングタームかつ広い視野をもって社会的価値や環境価値を見るべきだという人も徐々に増えてきました。もっと深く言うと、未来社会の、たとえばウェルビーイング(心身が健康で幸福な状態)とか、「幸せとは何か」を企業として追求すべきだという人の意見が、徐々に聞こえるようになってきたと感じます。
ただ、日々、生活に困っている人たちにとっては「そんなことより、まず食事」ですよね。だから、私は社会的・経済的格差の是正にも並行して取り組みながら、あるべき社会を議論すべきだと考えています。
――当研究所のシニア・グローバル・アドバイザーを務めるマルクス・ガブリエル独ボン大学教授は、道徳を前面に打ち出した「倫理資本主義」を提唱しています。
「近代経済学の父」と呼ばれるアダム・スミスの『道徳感情論』を読んで思うのは、倫理が資本主義の大前提に来ないといけないだろうと。倫理観を持った会社経営は、非常に重要だと思います。
一方で、人間だけをとらえて、あるいは、労働者と資本家という形でとらえて会社経営を考えればいいという時代では、もうなくなります。これからは、ロボットとAIが一体になってフィジカルな世界に入りこんできますからね。単に人間の価値観だけではなく、ロボットやAIの価値観まで含めた多層化を考えないといけないのかなと思うんです。
たとえば企業の経営会議でも、経営者が生身の人間の役員から意見を聞くだけでなく、AI1号、AI2号、AI3号の意見も聞いたうえで、最後は倫理的に判断できる能力を持たないといけない。それぞれのAIが出す意見はバックグラウンドのデータによって左右されますから、AIの性向も踏まえて判断する能力が経営者には求められます。これは、なかなか難しいですよ。
もう一つ、経営者が注意しなければならないのは、判断した当時は「正しい」と思っていても、5年後の基準だと間違っているかもしれないということです。そこで必要なのは修正力と、異なる人の意見も聞く傾聴力ですね。絶対的に信じたことが崩れるというのは、我々日本人が第二次世界大戦で経験しています。何が正しいかは、時代とともに変わる。そういう意味で、倫理も生き物だと思います。
――哲学には昔から親しんでいたのですか。
ええ。西洋哲学も、たとえばカントとかは好きです。ただ、西洋哲学は大まかに言うと、「神との対話」が中心になっているんですね。自分と神が対話することによって、自分の進む方向、どうあるべきかを決める。しかし、私の考え方は東洋文化的というか、意思決定というものは、1人ではなく相手がいて成り立つものだと思っているんです。「人間」も「人の間」って書きますよね。私は東洋哲学に非常に近いものを感じていました。
――東原会長は読書家としても知られています。
私の愛読書の一つに安岡正篤の『知命と立命』(人間学講話)があります。なぜ自分はここに生まれてきて、この仕事に携わったのかを認識するのが「知命」。そして、自分に与えられたミッションを実行するのが「立命」。実行するために一生懸命努力すると、「宿命」が「運命」に変わるし、良い運命になっていくよというのが、この本の私の理解です。
京都哲学研究所の取り組みになぞらえると、「哲学がないと、経営が成り立たなくなる時代が来る」と認識して京都哲学研究所に参画したことが「知命」に当たります。そして、この秋に開催する京都会議は、我々に与えられたミッションを実行するという意味での「立命」です。会議の場で参加者の皆さんとの間に共感が生まれ、活動の幅が世界に広がっていけば、必ずや将来、良い「運命」が来る。私はそう信じています。
Others