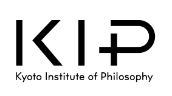AI、真正性、自己――英オックスフォード大で未来を再考 出口教授とKIP研究員が参加

英オックスフォード大学サイード・ビジネススクールで5月27、28日、「AI、真正性、自己に関するシンポジウム」が開催されました。京都哲学研究所はオックスフォード大学コーポレート・レピュテーション・センター(Oxford Centre for Corporate Reputation=CCR)と共にシンポジウムのスポンサーを務め、共同代表理事の出口康夫京都大学教授とリサーチ・マネジャーの高木俊一京都大学助教、研究員のサミュエル・モーティマー博士(オックスフォード大学インテーザ・サンパオロ・リサーチフェロー)の3人が参加しました。2日間にわたり、「人工知能は、人間であることの意味をいかに変えるのか?」という、テクノロジー、倫理、アイデンティティにまたがる問題を探求しました。
Details
ニュース・記事内容
シンポジウムは、気鋭の哲学者アグネス・カラード准教授(米シカゴ大学)による「LLMはTTMである」と題された挑発的な講演で幕を開けました。カラード准教授はチューリング・テストを「チューリング・テスト・マシン」問題として再定義し、AIの対話能力が真の思考に相当するのかを問いかけました。機械知能に関する長年の議論に一石を投じたこの講演は、常に限界を押し広げようとする本シンポジウムの基調を決定づけました。
出口教授は持論の「WEターン」についてプレゼンテーションを行い、モーティマー博士は「差別、中傷、そして自己」をテーマに議論を展開しました。続いてオックスフォード大学CCRのルパート・ヤンガー所長が司会を務めるパネルディスカッション「哲学と公共政策の連携」が行われました。出口教授のほか、スイスのジュネーブ・サイエンス・ディプロマシー・アンティシペーター財団(Geneva Science and Diplomacy Anticipator= GESDA)からマーティン・ミューラー科学予測担当エグゼクティブ・ディレクターとマニュエル・グスタヴォ・アイザック科学・哲学リーダーが登壇し、AIのような新興技術がもたらす課題に取り組むには学際的な協力が重要であることを共に強調しました。
その後、現代の形而上学および意思決定理論において最も影響力のある哲学者の一人である米エール大学のローリー・アン・ポール教授が基調講演を行いました。ポール教授は論文「体験知による価値(Value by Acquaintance)」で、新しいテクノロジーとの出会いや新しい仕事を始めるといった変容を伴う経験の価値は、直接的な体験を通じてのみ完全に理解できると主張し、これを政策立案やビジネスの意思決定に応用すると、人々が自身の未来を実際にどう評価するかという点が問われる場面では常に、実体験(およびそれを持つ人々)を審議の場に加えることの重要性が明らかになると主張しています。この日も、こうした持論について講演しました。
シンポジウムではこのほか、オックスフォード大学のイグナシオ・コフォーネ教授(AIの公平性と最適化について)、同大学のティモシー・ウィリアムソン教授(意思決定理論と自らが知っていることに基づく行動について)、英ブリストル大学のリチャード・ペティグリュー教授(AI、同意、選好形成について)、南カリフォルニア大学(米国)のラルフ・ウェッジウッド教授(高次の価値としての真正性について)、米ミシガン大学のエリザベス・アンダーソン教授(AIがいかに労働の質を低下させ、労働者の尊厳を損なうかについて)ら現代の哲学や法思想を代表する学者たちによる講演が行われました。これらの議論は、AIの未来が技術者だけで対処できるものではないという認識を示すものでした。真正性、公平性、人間の尊厳といった問題は、組織や市場、社会が人間と機械の双方をどのように評価するかという問題と不可分なのです。
開会と閉会の挨拶を行ったオックスフォード大学のアラン・モリソン教授が強調したように、組織にとって真の課題は、単にAIを効率的に導入することではなく、信頼と正当性を支える価値観の向上を確実にすることです。今回のシンポジウムは、真剣な哲学的取り組みが抽象的で難解なものでは決してなく、真正性、正義、そして人間の自己意識を守る形でAIの未来を形作るためには、哲学が不可欠であることを証明したと言えるのではないでしょうか。
Others