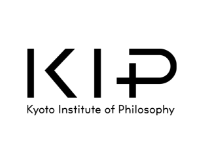AIの存在論的地位とは――米NYに続き京大で哲学セミナー L.A.ポール教授が講演

京都哲学研究所は9月22日から26日の5日間、米ニューヨークの研究機関「哲学・新人文学研究所(Institute for Philosophy and the New Humanities)」とともに京都市で集中セミナーを開催しました。米エール大学のL. A. ポール教授が基調講演したほか、当研究所の共同代表理事を務める出口康夫京都大学教授とシニア・グローバル・アドバイザーを務めるマルクス・ガブリエル独ボン大学教授が、それぞれワークショップのリード役として登壇しました。
Details
ニュース・記事内容
この集中セミナーは、ウド・ケラー財団(独)の支援のもと毎年秋に実施されており、今年は9月上旬にニューヨークのニュースクールで行われた1週間のセッションに続いて、京都大学に舞台を移して開催されました。ボン大学、ニュースクール大学、京都大学から大学院生をはじめとする若手研究者16人が参加し、集中的な議論を行いました。
京都セミナーのテーマは「AIの社会存在論」。AIのユーザー・インターフェースは、人と人との対話であるかのような錯覚を促すよう設計されていますが、実際には、人間的・非生物的・デジタル的なノードが結合した巨大な「社会的」ネットワークとの関与であり、その背後には人間の知的労働、データセンター、エネルギー資源などのインフラが存在します。国内外から参加した16人は、こうした社会性のモデル化や存在論的地位、人間知性との関係といった根本的な問いに向き合いました。
ポール教授の基調講演は初日に行われ、一般聴講を含め約40人が耳を傾けました。ポール教授は、経験する前はその本質を理解できず、経験後に主観的認識や選好が根本的に変化してしまう「変容的経験」の概念について論じました。講演後は認知科学や哲学を専門とする米ペンシルバニア大学のフリッツ・ブライトハウプト教授らを交え、自我の連続性や経験を選択する際の合理性をめぐる活発な議論が展開されました。さらに出口教授とガブリエル教授を含む共同ディレクター陣によるレクチャーやワークショップが行われ、セミナー期間中に開催された第1回京都会議にも参加しました。
最終日には、参加者一同で京都市北部の貴船神社と鞍馬寺を訪れ、霊的な風景の中で思索を深めました。ニューヨークと京都での2週間を通じて、若手研究者たちは学術的にも文化的にも交流を深め、再会を誓い合いました。
京都大学から参加した大学院生3人は、それぞれ次のように感想を述べています。
「ポール教授の『変容的経験』理論と出口教授の『Self-as-We』を接続し、AIに媒介された社会を考察した。AIは集団的変容を促しつつ、WEレベルの協働に依存している。AIがWEの力を増幅する社会で、いかに行為すべきかが今後の課題だ」
「AIが感情を予測し言語で表現できるようになるなど、より人間に近い存在となりうる状況が提示された。AIと社会規範の関係をめぐる議論を通じて、AIを人間と等しいものとみなすのか、単なる物なのか、集団的行為の産物と捉えるのかといった、洗練された観点を得ることができ、今後の自身の研究に対しても大きな示唆があった」
「変容的経験に面して私たちはどう決断するのか。『われわれ』としての行為者=自己の中で、誰がどのように道徳的義務を負うのか。そして、価値多層社会をどのように構想するのか。存在から価値に及ぶこれら多様な議論と国際交流を体験し、その濃密さの中で、一見遠く離れたアイデアや価値観同士がおのずから結びつく体験が得られた」
Others