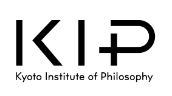京都哲學會刊行の『哲學研究』に掲載 出口、ガブリエル両教授の論考
京都哲学研究所の共同代表理事を務める出口康夫京都大学教授と、研究所シニア・グローバル・アドバイザーでもあるマルクス・ガブリエル独ボン大学教授の論文が『哲學研究』(第六百十四號、2025年7月28日刊行予定)に掲載されました。
Details
ニュース・記事内容
『哲學研究』は京都哲學會が発行する雑誌です。京都哲學會は1916年(大正5年)に京大文学部の旧哲学科を母体として設立された学会(https://www.bun.kyoto-u.ac.jp/kyoto-tetsugaku-kai/)で、現在も旧哲学科の流れをくむ専修の教員が委員を務めています。
出口教授の論文は”WE-turn of Values: Principles”と題されたもので、自身が提唱している行為のWEターンが価値論においてもたらす帰結を論じています。この論文において出口教授は、価値の概念を身体的行為と結びつける「価値のエナクティヴィズム(enactivism)」を採用し、そこから倫理的善、責任、権利、自由、ウェルビーイングといった様々な価値概念へのWEターンを導き出しています。さらに、ウェルビーイングのエナクティヴィズムとして「ウェルゴーイング(well-going)」という動的なウェルビーイングの概念を提唱しました。人間とAIやロボットを含む人工物との理想的な関係として、「主人―奴隷モデル」に代わる「フェローシップモデル(共冒険者モデル)」も提案しています。
ガブリエル教授の論文タイトルは “The Universal as an Ongoing Achievement: The Practice of Generating and Universalizing Ethical Knowledge”です。ガブリエル教授は、普遍的なものを「あらかじめ与えられた原理」ではなく、具体的な状況における行為主体の実践を通じて絶えず生成される「達成」として捉える立場から、倫理的普遍主義の再検討を行っています。カント倫理学や功利主義に代表される「一般主義(generalism)」が、一般原理から個別の義務を演繹しようとする試みが、パンデミック下の政策判断などが示すように実践的に有効ではないことを指摘したうえで、倫理的判断は固定的原理によらず、状況ごとに構築される「普遍化」の営為に基づくべきだと主張しています。その上で、「道徳的事実」の存在を認めつつも、それが単一の体系に還元されることなく、相互依存的かつネットワーク的な現実の中で絶えず更新されるという見解を示しました。
Others